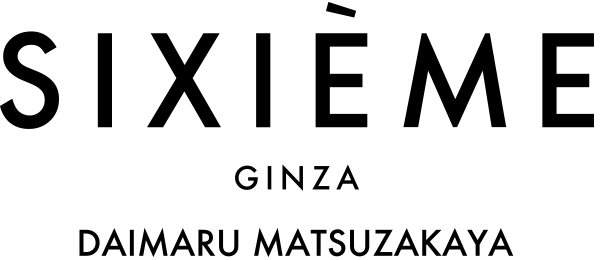SIXIÈME GINZA MAGAZINE 034
上質なものをカジュアルに。自然体で自分らしくある豊かさ
Interview with Mariko Nakayama and Shin Jinushi
各方面でご活躍のSIXIÈME GINZA世代の方々をお招きし、これまでの生き方や仕事に対する姿勢などをお話しいただくこのコーナー。今回はSIXIÈME GINZAのMDディレクターを務める佐々木が聞き手となって、「マディソンブルー」のデザイナー・中山まりこさんと、フォトグラファーであり「マディソンブルー」の副社長でもある地主晋さんにお話を伺いました。
以前もこちらのコーナーで中山さんにはご登場いただきましたが、今回はSIXIÈME GINZA世代の理想、というほど素敵なご夫婦でいらっしゃる中山さんと地主さんのお二人にお話しを伺う機会をいただきました。「マディソンブルー」のこと、最近の50代女性たちのファッションやマインドについて、そして子育てやご夫婦の関係性、今後挑戦してみたいことなどについてお話しいただきました。

普遍性があるからこそ、常にフレッシュでいられる
表参道から一本裏に入った閑静な通り、ストア2階のプレスルームにお邪魔した私たちを迎えてくれたのは、白で統一したミニマムな空間、むき出しの天井から吊られた金属ポールにハンギングされた最新コレクション、所々にセンスよく配されたアンティーク家具とゆったりとしたソファ。そして、いつも一緒に出勤しているという愛犬のハナちゃんでした。
2014年、6型のシャツからスタートした「マディソンブルー」。長年にわたってスタイリストとして第一線で活躍されてきたキャリアを生かし、ご自身のブランドを立ち上げられて今年で6年目。ハイカジュアルをコンセプトに、“着る人の内面に宿る女性性を同時代性とともに表象する普遍的な服”というストーリーを背景に「マディソンブルー」は大人の女性たちから絶大な支持を集め続けています。今、ますます高まる人気を中山さんはどのように捉えていらっしゃるのでしょうか。
「ブランド立ち上げ当初と気持ちは変わらないので、6年経った気がしないんです。もちろん、作るアイテム数も増えて、当初のメンズから着想を得たデザインだけではなく女性の身体が美しく見えるラインを始めるなど、常に新しいことはやっているけれど、マインドは以前と同じです」。
“質の良いものをカジュアルに”を提案し続けている「マディソンブルー 」は、シーズンやその時の気分によってトレンド感あるアイテムや女性らしいデザインが出てくるけれど、立ち上げ当初からブランドの代名詞となっていたワークシャツやオックスフォードシャツ、タイトなひざ下丈のスカート、メンズテーラードを彷彿とさせるジャケットなど上質でメンズライクなディテールが利いた定番がいつもブランドの中心にあります。

「ブランドの軸になっている定番のアイテムが愛され続けているな、と感じることが多いです。現在でも、支持されているアイテムはワークシャツやバックサテンのタイトスカート、50年代を彷彿とさせる7分袖シャツのJブラドリーシャツや端正なマダムシャツ、などブランドを代表する定番アイテムでそれらは毎年よく売れています。SNSでもJブラッドリーのシャツやタイトスカートのスタイリング写真を多くのお客様が投稿されていて、それらの写真を見ると改めて美しいなと思います。定番に最新シーズンのアイテムを上手に組み合わせて自分らしく着こなしている皆さんの姿を見ていると、これから先のことを考えた時のヒントにもなり、学びになっています。デビュー当初に作った“永遠不滅のカジュアルスタイル”の基本に立ち返らせてくれるのは、お客様の存在です」。
普遍性があるスタイリングだからこそ、時間を経ても変わらない部分がある。それがブランドの核となり、揺るぎない世界観が幅広い層に支持されているのでしょう。顧客は目の肥えたファッション業界人はもちろん、20代〜70代までの老若男女にまで広がっています。
「流行りによって移り変わるものもあるけれど、変わらない部分もあります。基本に新たな要素をプラスすることで、さらに奥行きが生まれるのでしょう。ミニマムなのに、コーディネート次第でいつでも新鮮に見せることが出来るところがブランドの魅力でもあるのかな、とマディソンブルーを着こなす周りの皆さんを見ていて気づかされます」。 揺るぎないブランドの軸は保ちつつ、時代によってシフトチェンジを続けているからこそ、常にフレッシュでいられるのでしょう。

50代女性が求めているものは
ご自身のスタイルを持ち、おしゃれなライフスタイルの見本のような中山さんは今や同世代の誰もが憧れる存在です。中山さんは、今の50代の女性たちのファッション感、マインドについてどのように感じていらっしゃるのでしょうか。周りのお友達やお客様から感じていらっしゃることとは?
「20代、30代、40代とそれぞれの時代で50代の人たちを見てきましたが、いざ自分が50代になって気づいたのは、周りがアグレッシブで若いということでした。私はスタイリストなので、以前からブランドもの、セレクトショップなどの境界線を越えてさまざまなお店をチェックしていました。それが特殊なことなのかと思っていたら、50代の皆さんが洋服を一番買う店がセレクトショップだということをある取材を通して知り、驚くと同時に自分が思っていた以上におしゃれにポジティブな世代なのだなと実感しました」。
また、50代になったらキレイ目な服を、という既成概念を覆すような高いカジュアル志向も感じられたとおっしゃいます。「カジュアルなアイテムの提案をした時の反応が想像以上に良かったのです。例えばデニムのミニスカートやGジャンを見て、可愛い、着たいと支持してくださったのも50代の方々でした。と同時に、同世代の方々は大人が着られるカジュアルなものがなくて困っていたということがわかりました。洗いっぱなしのシャツやGジャンで、大人が着て似合うものがなかったからでしょう。ブレザーも、はじめは若い世代への提案だったのですが、実際は50代以上の世代に響いていました」。
体型や肌質、髪質の変化もあり、これまで好んで着ていたブランドやコーディネートが急に似合わなくなる年頃でもある50代。とは言っても元来の好きなスタイルは変わらず、カジュアルを大人として楽しみたい。そこにマディソンブルーが救いの手を差し伸べてくれたのでしょう。
「私たちより少し上の世代はアメカジ全盛期でした。その後にヨーロッパのデザイナーものがきて、日本のデザイナーズブランドが台頭してきました。若い頃はラグジュアリーがあまり買えなかったので、日本人デザイナーズとインポートを使い分けて着ていました。自然とセレクトショップでも買っていましたが、現在の年齢になってからはセレクトショップに行っても自分には少し子供っぽくてしっくりこないのです。だからと言って全部をブランドもので揃えるのにも抵抗がある、というのが50代女性たちなのではないでしょうか」。

価値観を形成される20代の頃に華やかなバブル時代を経験し、上質な体験をしているからこそ、感性が豊かで、文化レベルが高いのも今の50代の特徴。だからこそ、お店に求めるレベルも高くなってくるのでしょう。中山さんは、最近SIXIÈME GINZAを訪れて感じたことがあるそうです。 「セレクトショップを見ていてもどこか自分向きではないなと思っていた時に、SIXIÈME GINZAに行ってみたら、グッと心に刺さるものがありました。私はヴィンテージ食器が好きなので店内の食器を見ていたのですが、食器と洋服とアクセサリー類が同じように置かれているのが自然だなと思ったのです。私にとっては、例えば50万円のコートの横に、10万円のアンティークのバカラのグラスがあっても全く違和感がないんです。それらを同じ“好きなアンティーク”というジャンルとして見ているからです。洋服というジャンルの中で好きなものを選んだり迷ったりするのではなく、自分の生活を取り巻く全てのものの一つとしてモノを捉えているのです。食べること、着ること、寝ることを全て同じこととして考えているので、洋服の横に器があるのがナチュラルに見えました。そして、ちょうど老眼鏡につけるカッコいいチェーンを探していたら思いがけずSIXIÈME GINZAにありました。50代のライフスタイルに寄り添って、さらにおしゃれな人をターゲットにしたセレクトが響きますね」。

ご夫婦の出会い、そして今
マディソンブルーのお仕事も一緒にされている中山さんと地主さんご夫妻。中山さんが「仕事についても子育てについても、何でも相談しあって、沢山の会話をしながら25年以上一緒に時を過ごしてきた」とおっしゃるお二人の馴れ初めは?
「最初に会ったのは屋台のおでん屋さんでした。今はないお店なのですが、80年代に神楽坂で芸者さんをされていた方が始めたおでん屋さんで、そこにはアパレル企業の社長さんや、クリエイティブ業界の方々が夜な夜な集っていて、面白いお店でした。お客がシャンパンを持ち込んで飲んでいるなど、自由な雰囲気なのです。当時はクリエイティブな仕事をしている人たちのコミュニティーが小さかったので濃縮されていて面白かったです。場所がおでん屋であろうがバーであろうが、出会いや刺激があるコミュニティーが形成されていました」と地主さん。
「出会った時、私は19才の学生で地主さんはスタジオマン。私が学校を卒業する時も、これから何をしたらいいのだろう、と年上の地主さんに相談していました。それから10年くらいは友人関係だったでしょうか」と中山さんも振り返られます。
多忙なフォトグラファーである地主さん、同様に第一線で活躍するスタイリストの中山さん、2人のお子さんの子育てはどうされていたのでしょうか。
「いつもバタバタでした。子供の世話はできる方がやって、仕事が終わったらバトンタッチするという感じでした。私が撮影のコーディネートチェックを編集部で夜22:00に終えると地主さんに電話して“終わったから仕事に出かけていいよ”と伝えていました。いつも、1時間後のことに一生懸命で、大変などと考える暇もありませんでした。それで、気づいたら子供たちは育っていたという感じでしょうか。小学校に2人が入ったら早朝ロケを受けるようにしたので、おむすびとお味噌汁を置いて夜明け前に家を出て、7時ごろに起きた?とロケ地から電話をしていました。洋服の貸し出しとスーパーでの買い出しの時間が一緒にスケジュールに組み込まれていました」と中山さん。
地主さんは、「子供のお迎え時間に間に合わなくて、そのままロケバスで迎えに行ったこともあります。フォトグラファーは現場で撮影したらほぼ終わりという仕事ですが、スタイリストは撮影が終わってからも拘束時間が長いんです。もう、あの頃のことは記憶にないですね。飯だけはとにかく食べさせる、ということに必死でしたね」。
「とりあえず、元気が一番!という子育てでした。その分、自立心は養われたのかもしれませんね。現在子供たちは25才と23才なので、保護すべき対象ではなくなったけれど、精神的な面でのサポートは必要だと感じています。子供も同じようなクリエイティブな仕事をしているので、私が経験してきたのと同じで悩みも多いのでしょう。子育ては長いんですよ」と中山さん。


お子さんとの関係は、親と子ではなく次のステージに入ったと地主さんはおっしゃいます。「自分の子供は生まれたときから保護し擁護して守る存在ですが、小さい頃から一人格として見るようにしていました。どのように人格を尊重しつつ、社会に出せるような人として育てるのか、をいつも考えていました。子供が大人になった今は、人と人としての付き合いが始まりました」。
子育てを経て、ご夫婦の関係性には何か変化はあったのでしょうかという問いにはすぐに「夫婦の関係は全く変化がないですね」と即答されたお二人。けれど、お子さん中心だった子育て期とは違って、さらにご夫婦の趣味にこだわることが出来るようになったようで、今を楽しんでいらっしゃるご様子が伺えました。
「車、家具、食器など全てのものを、自分たちの趣味よりも子供のことを考えて選んでいました。目黒に一軒家を構えていたのも、子供の友達が遊びに来た時にマンションだとうるさくて周りにご迷惑がかかる。思い切り遊ばせてあげたいという理由で一軒家を買いました。子供がいたら白い家具や高価な椅子を汚されたり、良い食器を割られたり、そういうことで怒るのは嫌なので避けていました。ソファやダイニングも子供がいる環境を考慮して買っていました。けれど、下の子が高校を卒業した瞬間に、自分が好きなダイニングを買って、自分の好きなソファに座りたいなと思ったんです。この家は私たち(夫婦)のもの、そこにあなたたち(子供)が居候しているのよ、という考え方に変わりました。旅行も子供達と一緒だからどこがいいかなと考えていたけれど、今度私たちはここに行くけどあなたたちはどう?付き合う?と聞いています。もし行きたい人がいたら来てもいいよ、という感じになりました。大人の私たちが自由になれた。そういう意味ではやったあ!と思います」
お料理の腕はプロ並みだとファッション業界でも噂の地主さん、ご家庭では殆どの家事をこなされるそうです。手を動かして制作するのがお好きなようで、「目黒の家では、屋上にキッチンを自分で設計して建てました。配管や配線も自分で、塗装も自分でやっていたので、当時はペンキだらけのつなぎで打ち合わせに行って驚かれていました」と地主さん。
中山さんは、「昔、彼が一人暮らしをしていた時に、床材を変えるなど自力でリフォームしながら住んでいたことを思い出しました。私が焼き鳥を食べたいと言ったらモツの下処理を2日がかりでしたり、Tシャツを自分で染めたりする姿を見て、この人は自分で何でも出来る人だな、ほっといても大丈夫だなということがわかって結婚を決めたところがあります」という結婚前のエピソードをお話しくださいました。

贅沢だと感じること
多忙な毎日をお過ごしの中山さんですが、今どのような時間を贅沢だと感じていらっしゃるのでしょうか。
「外出自粛の期間を経て、先日久しぶりに旅に出ました。京丹後市の伊根湾の船屋でシャンパンを飲みながら外を眺めて同じところに座っていました。昼過ぎに寝て、ふと起きるとマジックアワーになっていました。その時、周りの風景や光が刻々と移り変わり、動いている地球の美しさに感動しました。自分はここに座っているだけで何もしていないのに、朝日が昇り、海の色が太陽の高さで変わる。定点にとどまっていることも贅沢だな、と気づいたのです。私はいつもパリに年間6回、さらにモロッコに寄って、日本に帰るとすぐにニューヨークへ、というように年間何万キロも動き続ける人生でした。けれど、コロナで海外に行くことができなくなった状況になり、今までは忙しすぎで出かけすぎだったということと、自分が動いていなくても地球が動いてくれているということに気がつきました。定点にいることが贅沢なんです。自宅にいる時も散歩して部屋の片付けをして、6時過ぎにはベランダで日が暮れていくのを眺める。いつも考えて判断することの連続で、頭を使う仕事ばかりだったけれど、様々なものを手放してもいいのだということを学びました」。
定点にとどまる豊かさに目覚めたとおっしゃる中山さんですが、今後の洋服作りにはそのような心の動きは反映されるのでしょうか。
「今年はガラッと変えたいと、コロナ前の昨年から考えていました。また最初の6型に戻そうかというアイデアもありました。けれど、コロナによって部屋着が取り上げられているのを見て、逆にもっときちんと洋服を作りたいという気持ちが高まってきました。このようなご時世だからこそ、ミニマムにしないで、着ることの楽しさを表現していきたいと思います。もっと夢のある洋服を作っていたいです」。

ライフスタイルを提案するブランドとして
今後やってみたいことは?と伺うと「挑戦してみたいものだらけ」と目を輝かせる中山さん。「この店も、今は洋服を通してスタイルを提案しているけれど、自分のスタイルや自分が感じたことをアート、ジュエリー、食器など幅広い世界観で紹介していきたいと思っています。現在もアーティストの作品展示や、ジュエリーのオーダーなどセレクトショップでしかできないようなことを行なっています。パリでアパートを借りたのも、アポイントメント制のサロンをやりたかったからなのです。目指しているのはマディソンブルーというスタイルの提案を、洋服に限定せずにしていくということなのです」。また、「クラブ世代の私たち大人が、美味しいお酒を飲みながら集う、社交場のようなものがつくれたら素敵だなとも思っています」。
ファッションにとどまらず、スタイルのあるライフスタイルを提案するブランドとしてマディソンブルー は進化していくのでしょう。
これまでさまざまな一流を体感されてきた中山さんご自身にとっての本物、上質、一流、とはどのようなものなのでしょう。「敷居がないことだと思います。崇め奉られるモノは世の中いろいろあるけれど、それは一流ではないと思います。それよりもそこに存在して、素晴らしいと誰もが思えるモノこそが一流です。排他的にならず、来るもの拒まずの姿勢で、そこに存在して動かない存在。どのように使われでもいいという寛容さが大切だと思います」。
マディソンブルーも着る人を限定せず、身近に感じられる洋服としての存在を貫いてきました。「お客様のターゲットを決めたくないのです。着たい人に着て欲しい。文化系からサーフショップのお兄さんまで着てもらえてこそ本物だと思っています」という中山さんの言葉通り、自然体でそこに存在する。それはマディソンブルー そのものであり、また中山さんと地主さんご夫婦が醸し出す空気感そのもの。揺るぎない世界観が、多くの大人たちを惹きつけてやまないのです。

マディソンブルー 代表取締役 / クリエイティブディレクター / デザイナー
中山 まりこ(なかやま まりこ)
1980年代よりスタイリストとして活動。1980年代後半、ニューヨーク在住時にアメリカの雑誌『Interview Magazine』等でスタイリスト活動・ 雑誌のコーディネーターの他、NOKKO全米デビューのディレクターとして活躍。1993年KiKi inc.所属。広告・雑誌・音楽のスタイリングをメインに活動。2014年自身のブランド『MADISONBLUE』を立ち上げた。2015年著書『大人のおしゃれRULE BOOK A to Z』発売。

マディソンブルー 取締役 / フォトグラファー
地主 晋(じぬし しん)
武蔵野美術大学造形学科卒業後、スタジオマンを経て、1990年独立。ファッション雑誌、ミュージック・ビデオ、広告ほか、幅広いフィールドで活躍。奥様で元スタイリストの中山まりこ氏が2014年にローンチした「マディソンブルー」に参加。