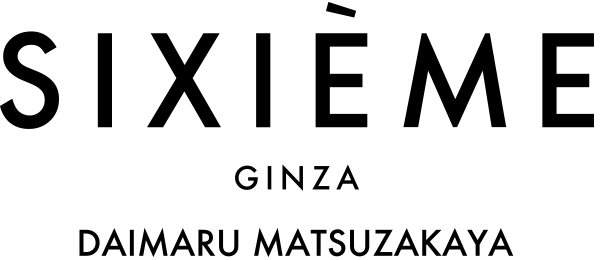SIXIÈME GINZA MAGAZINE 017
喜びはいつも日々のなかに
Interview with Maho Sato
SIXIÈME GINZAにお越しくださるお客さまにも多くお見受けする、ポジティブで、明るくて、輝いていて、どこか底力があるアラフィー世代。その実像をくっきりと世に打ち出した雑誌éclatを率いる佐藤真穂編集長に、編集という仕事の奥深さや、アラフィー世代のこと、ご自身のことなどを伺いました。

編集長の仕事とは言わば蛇口をひねるようなもの
雑誌は幼い頃から大好きだったと話してくださった佐藤さん。大学に入ってからも、実家のあった東京近郊から都内までの通学タイムは駅の売店で買う雑誌をじっくりと読むことができる特別な時間でした。しかし、編集を仕事にすることになるとは夢にも思っていなかったそうで、就職活動の最後に受けた集英社でトントンと面接まで進み、晴れて入社。いまでは他の仕事をしている自分を想像できないとおっしゃいます。
編集の現場には雑誌に掲載される情報の何十倍もの情報が日々集まって来ます。そこへ、各編集部員が関心をもって取りに行く情報もあるので、実際にはものすごい情報量の中から、雑誌そのものや読者のニーズに合うと思うものを吟味して絞り込み、一冊の雑誌ができあがるそう。情報を水に例えるなら、編集長の仕事は言わば「蛇口をひねる」ようなものだと話す、佐藤さん。蛇口のひねり方次第でアウトプットが変わるので、そのひねり加減こそがセンスであり、編集長の持ち味が色濃く出るとも言えます。
そんな佐藤さんにも、現在に至るまでに試行錯誤の日々はありました。non-noで編集の仕事を会得し、MORE、BAILAで副編集長を務めます。「編集者の仕事が天職だと言い切る上司と働く機会に恵まれたことで、わたし自身が仕事の面白みに目を向けて、それを言葉にすることで部下たちにも良い影響があるのだと気づきました。それ以来、部下には“ポジションが変わると、見える景色も変わる”と積極的に伝えるようになりました。また、編集長になったことで、組織を運営していくことの面白さがわかり、腹の括り方や覚悟を持てるようになったと思います。本来、組織のバランスを大切に考えるタイプなので、部下の意見をすべて聞いたうえで決定できる人間でありたいと常々思ってきました。そんなある日、部下のあるひと言から、自分は立場が違うのだということを受け止めて、腹を括ろうと思う出来事がありました。どんなに嫌がられようと必要であればやってもらう、だけどその責任は自分が取る。全包囲型集音機から自分自身がスピーカーになるという覚悟です。それ以来、蛇口のひねり加減を決めるのがわたしの仕事と心得ています」。

輪郭を帯びてきたアラフィー世代の実像
好きなコーディネイトを聞いたéclatの読者アンケートを読んで佐藤さんが驚いたのは、30〜40代の働く女性を対象としているBAILAやMarisolと好みの傾向に大差がないことでした。「世代を大陸に例えるなら、これまではシニアが住む大陸と30〜40代が住む大陸とは海峡を隔てて向こう岸にあるような感覚で捉えられていましたが、実際には地続きなのだとわかりました。しかし、広告主へご挨拶に行くと、éclatはまだまだシニア層の手前くらいの感覚で捉えられ、“シニア雑誌”とカテゴライズされていました。いまでこそ、女優の石田ゆり子さんのようにプライベートをInstagramで発信する女性が出てきましたが、3年前の就任時には、芸能界やモデルでアラフィー世代の実像となるような自身を発信する女性はどこを見渡しても居ませんでした。そんなことから、éclatがシニア雑誌と位置づけられてしまうのは、きちんとした“実像”がないからだと理解できたので、わたしの仕事はこの雑誌を通してそれをつくることだと認識することができました」。
顔が見えないところに輪郭をつくるには、まず、それらの像をむすぶ言葉をつくることから、と話してくださった佐藤さん。着こなしの雰囲気、年齢、属性、色、擬音語など、いろいろな切り口を考えました。その中から属性を言い得て、かつポジティブな意味合いを持つ言葉として浮かび上がったのが“マダム”でした。アラフィー世代でマダムと聞くと、受け取り方によっては少しお年を召した印象や、重々しいといったニュアンスもありますが、海外では良い意味で使われ、世界に引けを取らない日本女性たちのおしゃれ度を誇りにしたい。とりわけパリの薫陶を受けて育ったアラフィー世代にとってポジティブな響きでもあるという結論に至り、「Jマダム(=JAPANマダム)」という呼称になりました。「これはスタッフが同じ方向に向いて進むための約束であり、読者と自分たちをつなぐ約束であり、クライアントさんと方向性を確認するための約束です。消費されることなく、大切に長く使っていきたい言葉です」。
雑誌は生きものと言われますが、編集長が変われば雑誌も変わり、常に更新されていきます。「Jマダム」という呼称のリリースを経て、ウェブのリニューアルに伴い、表紙を一新したéclat。カバーモデルにはプレéclat世代にも支持がある富岡佳子さんを起用します。「富岡さんのように素敵に歳を重ねたいという若い読者からの声も届きました。このひとみたいな50代になりたいと憧れられる存在は、若いひとたちに向けてとてもポジティブなメッセージになります。雑誌とカバーモデルというのは手を取り合って進む同志です。富岡さんにはこの先の素敵な自分をつくっていきたいという目標があり、éclatもそんな素敵な女性像をつくりたかったので、足並みも揃い、よいパートナーになれたと思います」。
SIXIÈME GINZAにお越しくださるお客さまからも感じますが、それまでおぼろげだった像が輪郭を帯びてきて、アラフィー世代もInstagramなどのSNSを通じて、ご自身のスタイルを発信する方が増えてきました。昨年(2017)の春に、アラフィー世代にとって大きな転換期が訪れたと分析する佐藤さん。「たとえば、SIXIÈME GINZAのようなアラフィー世代のためのセレクトショップが産声をあげ、アラフィー世代のデザイナーが同年代のための美しい服をデザインしたブランドが多数立ち上がり、éclatも共に大きくなりたいと思いました。ここまでポテンシャルが見込まれる市場が原野として残っていて、そこに光りを当てたいと思ってきたのでéclatもその一助となっていれば嬉しいです」。

背景や奥ゆきのあるものを知る喜び
歳を重ねることの豊かさについては、開業当初からSIXIÈME GINZAでも唱ってきましたが、éclatとの親和性が高い部分でもあります。読者に向けて発信する立場であると同時に、佐藤さんご自身はどのように感じていらっしゃるのでしょうか? 「あえて誤解を恐れずに言うと、興味を持つだけでなく、その興味を深められるだけの財力が備わったことでしょうか。たとえばファッションでも、絶対に自分が素敵になると思えば求めるだろうし、歌舞伎のチケットも高いけれど好きだと思ったら頻繁に観られるようになった。興味の幅を広く持つことは若い頃から続けているし、歳を重ねて狭まる方もいらっしゃるでしょうけれど、心がけひとつでキープできると思います。でも、興味を深めることは時間とお金と経験がないとできないので、内面の豊かさを求めるためには、やはり歳を重ねることが必要だと思います」。
佐藤さんがアラフィー世代につけたコピーは「お金を持った女子大生」。子育てや家庭など、自分が中心でないことに時間を費やしてきた時期が過ぎて、ふたたび自分中心のライフスタイルが戻ってきた世代。女子大生の頃カフェに集まってはよく話していたように、ひとたび気の置けない友人が集えば、デジャヴュかと思うほど昔と変わらず、他愛のないおしゃべりに花が咲きます。「ただし、話す内容は違いますよ。昔は彼の話だったのに、いまは家族の話とか、将来や健康の不安なんかに変わりました(笑)。ひとたび、旅に行こう!となれば憂いもなく行けたりして、ある程度同じ感覚で美味しいものが食べられたり。昔と同じ感覚でいながら昔よりできることも増えて、なんて幸せな世代だろうと思います」。
SIXIÈME GINZAのコンセプトである「上質」「本質」「一流」。佐藤さんはそれぞれどのように捉えられているのでしょうか? 「どの言葉にも物語があることが重要だと思います。平たくなく、背景や奥ゆきがあること。この年代になると物語をひとと共有したいという気持ちが強いので、この3つの言葉を体するものには必ず奥があって、その奥を知る喜びがあり、その奥を知るための余裕が備わってきたとも言えます。先日、とある懐石料理のお店に伺う機会がありました。オーナーの女性はéclat世代よりも10歳くらい上だったと思いますが、季節の移ろいに合わせて素敵なアンティークの器に旬の食材を用いたお料理を載せて供され、そのすべてに理由があって、その背景に想いを馳せると、文化的な背景や歴史などの知識がまだまだ足りない自分がいて、もっと学びを深めていきたいと思ったところでした。そういうこともそつなくできるわたしたちの先輩世代の素晴らしさにはやはり憧れます。本当はライブに行ったりするほうが好きなのですが、最近では歌舞伎を心から面白いと思えるようになった自分もいて、歳を重ねるということは新鮮なことでもあると実感しています」。
最後に、佐藤さんにとっての原動力を伺ってみました。「かっこいいことを言いたいと思って考えたのですが、何度考え直しても日々の小さなことが結局一番嬉しいんですよね。それは、やはり雑誌づくりの現場にあって、スタッフがチェックのためにレイアウトページをデスクまで持って来てくれる時なのです。企画を立て、撮影した素材とダミー原稿がレイアウトされた状態で見るのですが、わたしが撮影現場に行ったわけでもありませんし、このコーディネイトでと具体的に伝えたわけでもないのに、期待以上のことが形になっている時には、“本当にいいページをつくってくれたねー!ありがとう!”と、素直にスタッフに感謝を伝えます。あの喜びを感じると、次もがんばろう!って思えるんですよね。雑誌づくりって、読者の方が想像する以上にたくさんの方々のお力を借りないとできません。編集長席から編集部を見渡すと、編集部員に加えて、数多くのフリーの方も出たり入ったりしていて、そのスタッフの奥にもさらに何百人ものひとがいて。これらすべてのひとたちが生業としてこの仕事を選んでくださり、それぞれの人生をかけてつくってくださることを一冊に踏襲しているのですから、ものすごく価値があるものなんです。雑誌は高いと言われることもありますが、そう考えるとむしろ安いくらいだなと思います」。
おかげさまで、SIXIÈME GINZAこの4月で1周年を迎えました。éclatと共に、アラフィー世代が毎日を豊かに楽しむことができる日々に、彩りを添えることができるようなストアでありたいと思います。

éclat編集長
佐藤 真穂(さとう まほ)
non-no、MORE副編集長、BAILA副編集長・編集長を経て、2015年からéclat編集長に。