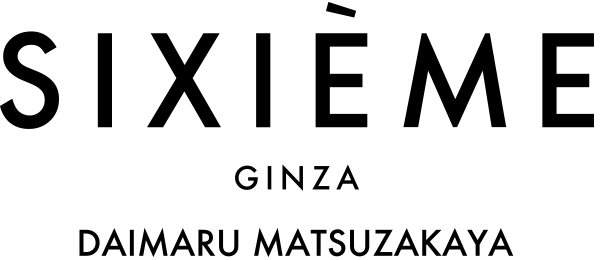SIXIÈME GINZA MAGAZINE 033
新しい体験を諦めない姿勢、それこそがラグジュアリー
Interview with Yuka Okada
各方面でご活躍されているSIXIÈME GINZA世代の方々をお招きし、これまでの生き方や仕事に対する姿勢、一人の女性としてのマインドなどをお話しいただくこのコーナー。今回はSIXIÈME GINZAのディレクターを務める笠原と佐々木が聞き手となって、編集者でプロデューサーの岡田有加さんにお話を伺いました。
稀代の映画プロデューサーで作家としても活躍する川村元気さんの対話集『仕事。』など話題の書籍を数多く手掛け、雑誌や写真集やSNSなど多彩なメディアや幅広い分野のプロジェクトの企画編集をされている岡田さんは、SIXIÈME GINZA が居を構えるGINZA SIXのブランディングマガジン「GINZA SIX magazine」の編集長でもあります。新型コロナとともにある生活の中で、人々や社会はどのように変化していくのでしょうか。岡田さんが感じていらっしゃること、今後求められるクリエイティブなどについて語っていただきました。

変わらないものに触れていたい
SIXIÈME GINZAも再オープンしてしばらくの時間が経ちました。ようやくふたたび、社会がゆっくりと動き始めた中で、これからのライフスタイルについて深く考えることも多い時期かと思います。この危機をきっかけに人々の生活と行動が一変していますが、価値観や意識にまでも変化の兆しが表れているのではないでしょうか。岡田さんは春からの時間をどのように過ごされていたのでしょう。
「予定していた国内外の出張、取材やプロジェクトがいったんストップして、当初はワークスタイルの変化にストレスを感じたりもしましたが、メールやラインに追われることもなくなり、そのうちどこかPCやケータイを持つ前の時代に戻ったような、時間の隙間のようなものが愛おしく思えるようになりました。お正月にも似た、ゆったりと静けさのある日常が心地よくて、“自分の根っこの部分では穏やかな時間を求めていたのかな”と気づかされました。職業柄、世の中の次の気分をつかまえようと全速力で生きてきましたが、これからは大きく時代が変わっても揺るぎないものに触れていたい、そういうものやことを伝えていきたいという気持ちが強くなりました」。
時代を経ても変わらないもの。一過性ではなく揺るぎないものへの憧れが、岡田さんを思わぬ畑仕事へと誘ったようです。「外出自粛期間中は、無性に自然に触れたくなって、近所の公園によく散歩に繰り出したりしていたんですが、ある日、自宅の目と鼻の先にオーガニック食材の八百屋を見つけたんです。そんな店があるなんて、全速力で生きていた頃は全く気づかずにいて、そこで買った野菜の美味しさにすっかり感動して“家族や仲間にも食べさせたいなぁ”と、勢いも手伝って東京郊外に畑を借りてみました。土は太古の時代からずっと変わらず大地に根ざしていて、命が芽吹く場所でもあるので、そこに立っているだけで足元からエネルギーが伝わってくる。ひたすら雑草を刈り取る作業は日常の悩みからも開放させてくれますし、今はなす、トマト、そら豆、生姜、バジルなどの夏野菜を育てていますが、これから収穫に忙しくなります」。
皆がライフスタイルを見直す中で、変わらない部分こそが本物であり、その変わらない部分に人々は惹かれています。不透明で正解がわからない道を進むときには、柱や軸を持っているものに本物の価値を感じるものではないでしょうか。

日本のエンターテインメントは大丈夫か
外出自粛期間、ご自宅では再びブームとなっている韓国ドラマにももれなくハマったそうですが、日本のトップ俳優たちとも親交があり、彼らとカンヌ国際映画祭を共にし、世界のエンターテインメントの場で日本人の居場所を作ることもライフワークにしている岡田さんは、改めて思うところがあったと言います。「例にもれず“愛の不時着”を観ました(笑)。練り上げられた脚本も、脇役まで達者な役者陣も、ロケ地のスケールも、全てにものすごい熱量が貫かれていて、日本は完敗だと思いました。韓国の映画や音楽が日本を大きく引き離している状況は、ポン・ジュノ監督の“パラサイト〜半地下の家族”がカンヌだけでなく米国アカデミー賞でも作品賞を受賞したことや、BTSなどの世界的成功ではっきり顕在化しましたが、ご存じの通り、韓国は政権運営は不安定ながらも、文化支援に関しては20年ほど前(金大中政権以来)から巨大な国家予算を投じてエンタメ産業を支え続けています。つまり、信念を持って、次世代を育てて、準備を積み重ねて完成したものであれば、人々の心は動くし、黙っていても世界に届く。一方で、日本では新型コロナの対策でも政治家はエンタメを一切救済しなかった。そんな采配では、ますます少ない予算で短絡的なヒットを狙った作品しか生まれてこないんじゃないかと危惧しています。文化は苦しい時代であるほど私たちを救ってくれるものなのに」。

今後、人々に求められるクリエイティブは高いレベルでの変革を求められている、と痛感された岡田さん。作り手に必要なこととは何でしょうか。
「新型コロナは100年に一度の危機と言われますけど、私たちはこれまでにない大きな不安と隣り合わせで、否応なしに変化を求められ、政治やメディアを疑うことを覚え、考えを深めています。そのような状況下では、少しの癒しでは立ち行かなくなっています。今までのアウトプットの仕方やクリエイティブのままでは、人々の心に響くものは出来ません。商業施設もメディアもエンターテインメントもファッションも、新しい座組みで、深く練り上げて、痛んだ心や世界に寄り添うストーリーが求められてくるのではないでしょうか。私たちの生活にはこれからものすごい変革がもたらされると思いますけど、新型コロナという外圧をむしろチャンスと捉えて、自分自身のあり方も含め、膠着して動かなかったものを解き放っていきたいですよね」。
加えて「本当に頑張らないと変わらないけれど、声をあげて行くことが大事な時期」とおっしゃる岡田さんからは、関わりの深いクリエイティブ業界への愛が込められた、応援の気持ちが伝わってきました。


ラグジュアリーとは、諦めない冒険心と心意気
SIXIÈME GINZAは、本質を極めつつしなやかに生きる大人の女性たちに向けて、ニューラグジュアリーをキーワードに、これからの時代を豊かな気持ちで過ごすためのさまざまなご提案をしています。岡田さんにとって、ラグジュアリー(豊かさ)とはどのようなことでしょうか。
「当然ながら都会に暮らすとか最高級品を買うとかじゃなくて、次の体験に対して諦めない姿勢、それこそがラグジュアリーだと思っています。例えば、“年収がこのくらいだから、こういう体験ができない”と諦めてしまうのではなく、日常的にやりたいことを欲して、新たな出会いを積み重ねて、視野や行動範囲を広げる。例えば田舎のおじいちゃんが近所に行きつけの居酒屋あったとして、隣町に新しいお店が出来たら、“一度試しに行ってみようかな”という人はラグジュアリーな人で、“俺はいつもの居酒屋にしか行かない”と頑なな人はラグジュアリーじゃないというイメージ。ファッションでも、人から何か勧められたとして、“買ってみようかな”と好奇心を抱く人はラグジュアリー。自分を更新していくことに良い意味で諦めが悪い人は、いつ会ってもどこか成長していて、色褪せない。誰かにとって自分自身もそういう存在でありたいと思っています」。
ラグジュアリーとは、モノやコトに対する冒険心や心意気。日常のふとしたことにも好奇心を持って、トライしてみる。
「要するに、どんなに限られた状況でも、自分という対象を俯瞰で見て可愛がれる余裕やユーモアを持っている人が豊かということだと思います」。

多くの人に伝わらないと意味がない
大学を卒業されてからここまで、編集のお仕事一筋で来られた岡田さんですが、現在の職業につかれたきっかけは何かあったのでしょうか。 「実は編集者になろうと思ってなったというより、何人かの方々の導きがあって、気がついたら今の場所にたどり着いたという感じなんです。高齢の両親のもとに生まれた一人っ子だったので、今どきの情報を得るために、幼い頃から雑誌や漫画や小説を自主的に読んで育って、作文だけは好きでした。そんな私を見てくれていた高校の先生の推薦もあり、大学では小説を書く学部に進ませていただいたんですが、今度は悪友からマガジンハウスのアルバイトに誘われて、当時全盛期だった雑誌ananの編集部へ。さらにそこで編集のイロハを教えてもらった当時の編集長の紹介で、BRUTUSやPOPEYEやTARZANの創刊編集長で知られる石川次郎さんの事務所に転職し、20代を過ごしました。石川さんの元でのほとんど初めての仕事はエールフランスの機内誌のリニューアル創刊で、一冊150ページのコンテンツを編集するというものだったんですが、たった1人でパリに行って、現地の強者のジャーナリストの方々の訓示を受けながら、全企画を組み立てなければなりませんでした。何も分からなかった私に全面的に任せるという寛大な育て方をしていただいたからこそ、必要な失敗もできたし、今がある。師匠には本当に感謝していますし、ライバルがいるとしたら、それは過去の自分の仕事です」。
GINZA SIX magazineの編集長である岡田さんが、本づくりで心がけていらっしゃることは何でしょうか。
「いかに共感していただくか、ということを大切にしています。これは盟友でもあり、書籍の編集を担当させていただいている川村元気さんから学んだことでもあります。川村さんは、近年だと“君の名は。”や、“天気の子”などの映画を手掛けたヒットメーカーと評されていますが、彼はビジュアルひとつ、対談相手ひとつ、文字ひとつ、全てにおいていかに多くの人の気持ちを動かすかを考え、その能力に長けています。そんな川村さんとの長年のやりとりで鍛えていただいたこともあって、GINZA SIX magazineに関しても読者に“そうそう!”と心の相槌を打っていただける次の気分をどう掴まえて、どう表現したら多くの人に共感をいただけるのかを心がけています」。
毎号のテーマはもちろん、言葉遣いや1つ1つの文字、デザイン、写真、関わるスタッフの選び方にまで神経を使われています。「SNSやIT全盛の時代にあって、紙の雑誌は正直、オワコンですよね(苦笑)。でも、だからこそ発行の機会を与えていただいているGINZA SIXには本当に感謝していますし、GINZA SIX magazineでは、少しでも新鮮味を感じてもらえるような冒険をしなければ意味がないと思っています。売らなくてはならない一般誌ではなくGINZA SIXの顧客や銀座の近隣の方々に無料で届けていただけるブランディングマガジンでもあるので、情報過多なカタログ的手法とは一線を隠し、ページをめくる読者の時間に、シンプルに心地よく寄り添える一冊でありたい。商品そのものだけでなく、“GINZA SIXはわかってるな”という感覚を持っていただけたら、御の字です」。

編集長として、GINZA SIX全館に精通している岡田さん。いつもGINZA SIXで気ままに買い物をしているそうですが、「SIXIÈME GINZAは、まさに女性の次の気分をファッションや雑貨を通して提案している私の大好きなお店の一つです。GINZA SIXも、真ん中にSIXIÈME GINZAがあるから全体の波形が保たれているのだと思います。ちょうど、星形を描いたときに真ん中にできる台形のような。ちなみに新型コロナによってグローバリズムからローカリズムへの転換が叫ばれていますが、例えば地方などで作られたクラフトマンシップが光る工芸品や、未来の日本を担うだろう若いクリエイターの作品など、従来のセレクトショップとは違う自由闊達な冒険心を、いち消費者としてお二人のディレクターに期待しているところです」。
アート、文学、デザイン、エンターテインメントなどさまざまな分野のレジェンドと呼ばれる方々と交流がある岡田さんの考える一流の人とはどのような人なのでしょう。
「自己顕示欲のための仕事ではなく、社会や世界を良くするために汗をかくことを前提に生きている人。そういう意味で、例えば会社を大きくして、お金持ちになって芸能人と付き合うみたいなことは、個人的にはちょっと違うのかなと(苦笑)」。
編集者という仕事は、人と人、モノと人を繋げてムーブメントをつくる、いわば媒介のような存在だと言われています。最後に岡田さんに、「これから挑戦してみたいことは」と聞くと「自分で挑戦してみたいことは、実はさほどないんです。それよりも、ここからどんなに時代の流れが変わっても、人々や社会に活かしてもらえる自分でありたい。そのために、間違っても神棚の上に鎮座しないで、自分から汗をかき、時に悔し涙も流す生き手であり続けたいと思います」と、極めて編集者らしい回答が返ってきました。

編集者 ・ プロデューサー
岡田 有加(おかだ ゆか)
企画編集とプロデュースを主とする株式会社81代表。早稲田大学第一文学部文芸専修卒業。在学中より『anan』(マガジンハウス)編集部で学ぶ。その後、編集者の石川次郎氏に師事。2003年に独立後、各種媒体の創刊、雑誌をはじめ書籍や写真集の企画、各界クリエイターやブランドとのプロジェクトのプロデュースなど、メディアやジャンルを横断的に活動。主な編著にいずれも川村元気氏の対話集となる『仕事。』(書籍版/集英社、文庫版/文藝春秋)、『理系に学ぶ。』(ダイヤモンド社)など。2017年より『GINZA SIX magazine』の編集長、2020年4月からGINZA SIXの公式インスタグラムのクリエイティブディレクションも担う。
https://81inc.co.jp/