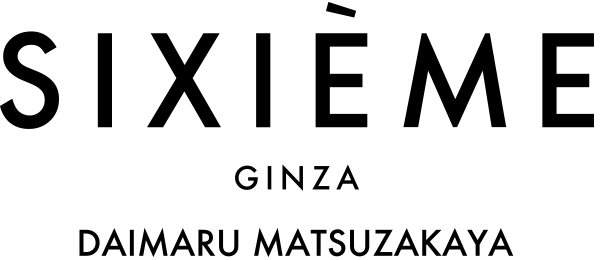SIXIÈME GINZA MAGAZINE 030
美しくて明るい方を見る、それが自分の役割(前編)
Interview with YOSHIYUKI MORIOKA
各方面でご活躍されているSIXIÈME GINZA世代の方々をお招きし、これまでの生き方や仕事に対する姿勢やご自身のマインドなどをお話しいただくこのコーナー。今回はSIXIÈME GINZAのMDディレクターを務める笠原と佐々木が聞き手となって、「森岡書店」店主の森岡督行さんにお話を伺いました。
銀座の中心部から少し離れた静かな界隈にある森岡書店は、週替わりで「一冊の本を売る書店」。一冊の本から派生する作品を展示しながら本の世界観を見せる空間には、森岡さんの審美眼に惹かれてお客さんが全国から集まってきます。執筆家、キュレーター、ブックディレクターなどさまざまな顔を持ち、多方面で活躍されている森岡さんのお話には、人生を照らしてくれる本の言葉、面白いエピソード、日常を楽しむ素敵なアイデアが散りばめられていました。その溢れる知識、好奇心、そして強い探究心はどこから生まれているのでしょうか。シジェーム世代を勇気づけるオススメの本も伺いました。

一冊だからこそ解釈は深まる
たった一冊の本を通して、人と人が出会い、そこから交流を紡いでいく。ある週は写真集、次の週は絵本、あるときはアート作品集というふうに週ごとに売られる本は移り変わります。作者を招いたトークショーなどのイベントがひらかれ、ときには店先に長い行列ができることも。そんな森岡書店の姿は、大量消費、スピード、利便性といった現在の主流であるマーケティングビジネスとは対局の位置に存在し、そのスタイルには強い想いと信念を感じます。
「世の中にはさまざまないい本があるけれど、1週間に1つに絞り、いいものをさらに良く見せることを考えました。一冊の本の良さをさらに多くの人に伝えていきたいという想いから開店に至りました」と語る森岡さん。バリエーションと無限の在庫数で勝負するのが書店という流れがある中、森岡書店の「一冊だけ」というコンセプトは一冊に絞ることでひとつの世界観に深く入り込み、深く体験することを目的にしています。一冊だからこそ解釈はより深まり、一冊を介するからこそ人間本来の臭覚が研ぎ澄まされ、感性がのびやかに解放されるのです。
森岡さんは神田・神保町の一誠堂書店に入社され、その後茅場町に「森岡書店」を立ち上げられたのですが、その頃の経験が現在の一冊だけの書店の実現を後押ししてくれたのだとおっしゃいます。「茅場町の店で刊行記念イベントを行っていたのですが、イベントを開催するたびに一冊の本に対して大勢の読者やファンが集っていました。多くの人が集まり会話がなされて売り上げもそこそこ立つということを茅場町での10年の経験から学びました。消費(モノ)から体験(コト)の時代への転換は20年前からありましたが、さらに体験の中に学びがあったり、気づきがあったり、そういうことが求められているのだろうなと思っています」。


現在の森岡書店が入居する建物は、東京都の歴史的建造物にも指定されている昭和4年築の鈴木ビル。昭和14年から日本工房という編集プロダクションが入っており、“出版の聖地”と呼ばれています。当時の日本の対外宣伝誌を制作していた日本工房には、名取洋之助、土門拳、亀倉雄策といった当時の第一線で活躍するクリエイターたちが集まっていました。「そういう歴史的背景のある場所で、現代の本を紹介することにも意義を感じました」。
もともと古い建築物がお好きだったとおっしゃる森岡さんですが、就職先となった神保町の古本屋・一誠堂も近代建築でした。その後も、近代建築物とはご縁が深かったようで「色々な近代建築の職場で働きましたが、1930年代の建物に入ると、時間と空間が今と違います。空間もどこか異国にいるような感覚に陥って、そのズレがいいなと思います。建築から得る身体的な体験とそれが精神に及ぼす感じがいいなと思っています」。
本の街、神保町にも思い入れがあったそうです。「近代建築と、本と、神保町が好きなのです。神保町の街に関して評論家の森本哲郎さんが著書『懐かしい東京を歩く』(PHP文庫)の中で“この地球上で、貴重な書物という文化財をこれほどぎっしり詰め込んだ地区は、神保町をおいてほかにはない。このような地域が都会の一画を占めているだけで、東京は文化都市と言っていいような気がする”と書いていらっしゃいました。私はその文章に共感して神保町という街に親しみを持つようになりました。渋谷や新宿のような大都会は世界中に存在し、奈良や京都のような歴史的観光地も海外にも存在する。しかし、古本屋や本屋が200店以上も集積している街は世界中どこを探してもありません」。

世界は二つでひとつ
近代建築で感じる光や色について話すうち、森岡さんの色彩の捉え方についての話題になりました。
「私は色弱なので、見えている色が人とは違うようです。赤と緑が特に分からなくて、微妙に写真も違って見えているはずだとは思います」と淡々とお話しされます。「先日ガラス作家さんと話をしていて、“私はあなたの作品の緑の質感が好きです”と伝えたら、作家さんが“私は緑の作品は作っていないです”とおっしゃっていたので、私の目には違う色に映っていたのですね」。
しかし、森岡さんはご自身の視覚のことを「私にとってはアドバンテージだと思っているのです。他の人とは見え方がちょっと違うということは面白いことだなと思うのです」。
どうしてもネガティブになってしまうことが多いけれど、面白いと思える感性や物事を肯定的に考えられるようになったのはどうしてなのでしょうか。「大人になってからそういう自己肯定感が高まったのだと思います。今までさまざまな本を読んできて、世の中は二つで一つだということがわかってきました。例えば表裏、善悪、清濁、男女、美醜、陰陽、といった2つの要素が合わさって1つがあるという意味です。人間の脳の構造も左と右があって物事を認識するようにできていますよね。そんな考えで言うと、私は良い方、美しい方向に考えたほうが絶対的に得だろうなと気づきました」。 善悪があるなら善を、明暗あるなら明るい方を見て自分は進むことにしようと決められたそうです。「世の中には、戦争や犯罪、飢餓など暗い部分もあるけれど、それらは政治家たちが担当して解決すればいいことなのではないかと思うようになりました。両方の側面があるなら美しくて明るい方を見る、それが自分の役割だと思っています」。
自己肯定感を高め、いつも明るい方向を目指して進んでいかれる森岡さんの姿勢は周囲にも伝播して、ポジティブな流れを生み出しています。

銀座について
60年代の銀座を題材にした写真集を現在編集中の森岡さん。「写真家、伊藤昊さんの作品を昨年の夏に埼玉で拝見して胸を打たれました。数々の写真では、1964年当時の銀座の光景が展開されていました。オリンピックの高揚感や東京の街が近代化していく様子が鮮明に記録されているのです。60年代当時に活躍していたカメラマンやフォトジャーナリストは、ユージン・スミス、土門 拳などがいて、社会問題や公害など社会の負の面と対峙する写真を撮ることが主流でした。その中で伊藤さんはその時代のファッションや文化など人々の喜びのシーンを切り取り、世の中のいい方を見るという立ち位置にいらっしゃって、そこに共感を覚えました。これは私が写真集にしたいと思い、頑張ることになりました」。
もともとは日本で最も古いタウン誌『銀座百点』の編集部に持ち込まれた写真だったのですが、銀座と写真のことが好きな森岡さんのところへお話がきたそうです。
昭和から令和へと時代は移り変わりましたが、銀座で変わらないものは何でしょう。「銀座には喜びと感動があると思います。喜びの先に次の時代の潮流があると思うので、それはどの時代も変わらないだろうなと思います。銀座には常に人を感動させ、喜ばせるものがあって欲しいと思います」。
常に光を見て、明るい銀座の風景を取り続けた写真家・伊藤昊さんのように、世の中のポジティブな面を引き出し、夢を見させてくれる場所が銀座なのでしょう。

森岡書店 ・ 店主
森岡 督行(もりおか よしゆき)
1974年生まれ。著書に『荒野の古本屋』(晶文社)、『BOOKS ON JAPAN 1931-1972』(ビー・エヌ・エヌ新社)などがある。企画協力した展覧会に「そばにいる工芸」(資生堂ギャラリー)、「畏敬と工芸」(山形ビエンナーレ)などがある。近年は洋服などのプロデュースを手がけることも多い。株式会社森岡書店代表。『工芸青花』(新潮社)編集委員でもある。